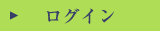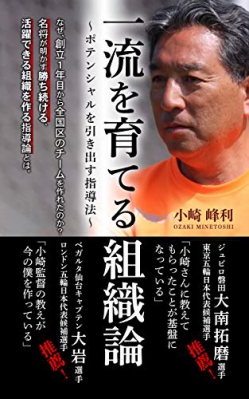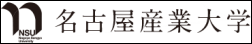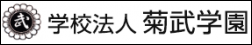サッカーという競技は個人スキルをベースに11人がピッチ上で相手との駆け引きを楽しみながらゴールを目指す競技である。
その為に低年齢においては個人スキル、個人戦術に重きを置いてトレーニングが進められる。
しかしながら味方との連携、味方の為にというトレーニングになると全く理解できない選手がたくさんいる。
個人に特化したトレーニングがマイナスになる要素も含んでいるということを最近つくづく思う。
自分がボールを受けたくてフリーの所に顔を出す動きは当たり前のようにできる選手はたくさんいる。
しかし相手の動きを見ながら味方の選手をフリーにさせる為に自分が動くということを意図的にやれる選手は少ない。
またそれをより一層確実なものにする為に動き出しのタイミングまで考えて動き出せる選手は更に稀である。
スキルのトレーニングは一生懸命にやるが、味方の為の動き方やタイミングをいつトレーニングするのか。
それは常日頃の生活の中のあらゆる場面でタイミングを探して、そして実行してみる。
ピッチ外のトレーニングがピッチ上のトレーニングに深みを持たせるか、選手はもう少しサッカーの奥深さを考えた上でトレーニングに向かうことをお勧めする。
我々指導者は目に見えないスキルアップが鍵であるということをしっかり考えながらコーチングできれば更なるレベルアップが望めると思う。
最近はどのカテゴリーにおいてもトレーニングを全体的に眺めて、観察をする。
時には俯瞰して上からトレーニングを見ることがある。
試合を上から観てポジショニングなどを確認することよりも色々な角度や距離を縮めてトレーニングを観ていると、トレーニングそのものの色、例えば熱く闘っているなら真っ赤であり、コーチの戦術に関する話を聞いている時は澄んだ水色に見える。
グループ戦術のトレーニングの時に、あるグループは和かにオレンジ色のように、また空気の密度は引き締まる事はなく空気も薄く感じる。
対人のトレーニングの時にバチバチとやり合い骨のぶつかる様な感じのトレーニングを見ていると、赤の中に激しい紫の色を見ているようだし、空気感も濃く引き締まった密度を感じる。
出来れば色に例える様に選手個々が色と密度を作ったり感じたりできる様になれば中味の濃いトレーニングができる様になると思う。
我々が取り組んでいるサッカーは1人の力だけでは上を目指すには限界がある。
真面目に黙々とトレーニングする選手がどのカテゴリーでも増えてきている。
以前から言っているように、自分のスキルを上げる努力はするが、仲間の能力やアクションを促すコーチングスキルのアップにはまだまだ乏しい。
1対1の攻防など見える部分のアクションを促すコーチングは可能だが、ポジショニングやカバーリングなど明らかに予測をした上でのコーチングスキルは黙々と頑張る選手には乏しいと感じる。
そのような選手はリアクションプレーが多いし、仲間のレベルアップに寄与する事が乏しい。
リアクションでは無く、アクションをする、させる事ができれば自ずとチームレベルは上がって行く。
ボールを触らずに前を向く感覚を持っている選手はやはり天性の感覚であるのか、しかしながら情報収集さえ出来ればボールを触らずに前を向く事は訓練で出来るはず。
前を向く事に時間を使ってしまうことが現代のハイプレスサッカーにおいて致命傷になりつつある。
サッカーは攻撃は前を向く、守備は前を向かせない。
盾と矛ではあるがその攻防の差が勝敗の確率の上下である。
やはり前を向く事は人生と一緒で大切。
人生は前を向き続けるには時間がかかる事もある。しかしサッカーは時間をかけず、ボールを触らず前を向けたらシュートのチャンスは増えるはず。
人生においても勉強においても沢山の見・聞をしてきた。
しかしながらその見聞きを実際に動として実行となるとかなりの比率で実行は少ないと感じる。
もう少し遡れば、見聞の時に頭の中にしっかり取り込んでいない可能性が高いように思う。
頭の中にしっかりと見聞が残っていないので動にまでいかないのか、はたまた頭の中に残っているが動に行けない勇気がないのか、失敗が怖いのか。どちらにせよせっかく見聞をしても動(チャレンジ)をしないとどうしようもない。
サッカーにおいては知識だけでは何ともならない。
我々育成年代の指導者は身体も頭も大人に近くなる前に見・聞・動をバランス良く身につけさせる事が肝要である。
随分前の小崎塾で書いたような気がするが、最近のサッカー選手、育成年代の選手のグランドレベルにおいての視野の狭さ。
グランドでマーカーを並べてトレーニングそのものをオーガナイズすることは今はほとんど無い。ほとんどどころか全く無い。
選手が黙々とトレーニングしている場面を凝視しながら選手の頭の中、心の中を見抜けるように彼らの一挙手一投足わ眺めていると、自ら視野を広めて、自ら情報を得て選択肢を広めている選手が少ない。
ピッチに立っている選手の中で大学生でさえ見えてない、見てない選手の多いことか。
年齢が若くなればなるほどその数は少なくなる。
視野を広げるというか情報収集に特化したトレーニングはしていない。
我々指導者の子供へのコーチングも少ないのでは無いかと感じる。
サッカーは自分で情報を収集することが優先され、その他に仲間から情報をもらうことによってプレーの選択肢を増やした上でチーム力をあげていかなければならない。
選択肢が増えることで状況判断がどういうことか理解できるはず。
低年齢時にボールを扱うスキルアップと同じぐらい観る聞く話すスキルを身につけて欲しいとつくづく思う。
動きの質
ゲームの中では歩く事もある。ジョギングする事もある。スプリントする事もある。
しかしながらすべての動きには意味がある。
歩きながらポジションをコーチングをする。ポジションを戻しながらコーチングをする。
ジョギングというかゆっくりと走りながら相手を動かす。
意図を持って動きながらスペースを作る。
相手を引き連れて味方の動きを手助けるる。
ゴールを目指してスプリントをする。
プレスバックの為にスプリントをする。
全ての動きには意味がある。
どのような動きにも質を求めて動く必要がある。
その為にはトレーニングの中から動きの質を改善する頭を持たなくてはならない。
アイツのボールタッチ独特だよね。
アイツのシュートのタイミングってキーパーワンテンポ遅れるよね。
アイツのパス、あんな所を見てるんだ。
アイツめっちゃ速いよね。縦に行かせたら止められないよね。
アイツ、ボール持つ姿勢が良いよね。
アイツ危険察知能力高いよね、インターセプト上手いよね。
アイツ身体強いね。
アイツのヘディング滞空時間長いよね。
これらは全てJr、Jrユース、ユース年代で交わされる会話であり、時にはアイツ天才だよねとか才能あるなとか、言われた選手である子供がいつのまにか競技サッカーからいなくなってしまう現実を多々見てきた。
確かに才能は存在する。
存在はするが、その才能を最大限に活かすには継続と努力が必要。
特にサッカーという競技は不確定要素が多い競技である。
チームの意思統一も必要、協調性も必要、ある意味のわがままも必要。
才能のある選手だけがサッカー選手になっているわけでは無い。ボールを蹴り始めてから数々の指導者の言う事を健気に聞いて来た選手が現在の上手いよね一という選手達。
大多数が才能と努力の継続をして来た選手である。
稀有な才能を持っていたとしても聞く耳を持たなかったり、努力の継続が出来ない選手は遅かれ早かれ上位の競技サッカー界からはいなくなる確率が高い。
よって努力の継続が最高の才能では無いだろうか。
育成年代(最終は大学生)であろうが、プロであろうがアスリートを目指す人間は、ある意味完璧を目指さないと上達速度が早くならない。
チームスポーツであれば中途半端は決してチームの為にもならない。
挨拶もしっかりでき、その挨拶も状況に応じて種類を分ける。
監督やコーチの話は徹底して聞く。
トレーニングは常に100%で臨み、リラックスや休養はしっかり取る。
身体に入るもの食事など栄養にも気を使う。
チームメイトや相手や審判へのリスペクトなどなど。
できれば育成年代に完璧に出来なくても、完璧を意識して行動することで、必ずや失敗が訪れる。
この失敗こそ成長曲線を上げることになる。
完璧は難しいが、意識させる事はできるはず。
頑張って言い続けよう。
育成年代の指導を始めた頃からだから約20年以上前になるが、「当たり前の事を当たり前にできるようにしよう。」とよく言ってきた。
朝起きたら「おはようございます」悪いことしたら「ごめんなさい」から始まり、時間を守りましょうなどなど社会生活の中での当たり前が沢山あり、サッカー面においても様々な当たり前があった。
最近におけるサッカーはかなり多くの当たり前が増えてきた、近代サッカーにおいては「ハードワーク」は当たり前、FWなど前線からのプレスは当たり前などなど、「当たり前」も時代と共に移り変わるのはあると思うが、古き良き時代からの当たり前が現在の子供達というか若者に上手く伝わってきていないと感じる事がよくある。
育成年代の人間教育とスポーツにおける進化は比例していると思う。
よって「当たり前」の事を当たり前にできるように具体的な事例を説明しながら根気よく話をしている今日この頃である。